経理業務の効率化事例を知りたい
経理業務の効率化と改善の手引き。債権管理のシステムを導入した場合の成功事例も紹介します。
経理業務の効率化&改善事例
近年、時間外労働の問題が頻繁に取り上げられ、さまざまな労働の現場で、業務改善の必要性が求められています。
経理業務も例外ではなく、とくに経理は、毎日違う取引先と顔を合わせる営業などとは違って、毎日の作業がある程度決まっています。そのため、仕事の中でも効率化しやすい業務だといわれています。


経理をはじめ、業務合理化の秘訣として「ECRSの原則」があります。
ECRSは、Eliminate(排除)、Combine(統合)、Rearrange(順序の変更)、Simplify(単純化)の頭文字を取ったもので、工程や作業をなくすことができないか、2つのステップを統合したり一緒にできないか、順序の変更はできないか、必要な作業を統合して単純化できないか、という観点からの見直しができないかというものです。
こうした観点から、経理ができる業務の改善例として、以下のものが挙げられます。
業務の効率化とか改善ってなんだろう…?
所属部署やポジションによって軸足を置く業務は変わりますが、経理部門をはじめとして入金管理に携わるポジションの人にとっては、業務効率の改善は使っているシステムへの依存度が大きなポイントです。
- 「現状でも業務過多だと感じているのに…」
- 「システムだと細かな部分がカバーできないから、エクセルも使ってる…」
- 「入金確認の追いかけに必要なフローが多重だから積もるとどうしようもない…」
色んな声が有りそうです。
より効率的なシステムが何かを改めて検討することも、価値的かもしれません。
経理ができる経理業務の改善例
キャッシュレス化を進める
経費の精算などで現金の扱いがあると、現金の出納や伝票作成などの処理をするための人件費も手間もかかります。
経費精算を月に1回にまとめたり、給与と合わせて支払ったりすることで、現金を扱う手間が減り、ミスを減らすことができます。
業務をまとめる
経費精算だけでなく、会計処理も1カ月に一度というようにまとめることができます。それによって、こまめに作成していた伝票も1枚にまとめることができます。
仕入れ先や外注先への支払いも1カ月に1回にまとめることができれば、振込作業や資金繰りなども一度ですませることができます。
管理するものをまとめる
管理するものが多ければ多いほど、業務も増えていきます。たとえば、管理する銀行口座が複数あれば、その分だけ確認が必要になります。
メインバンクをひとつに決めて、入金用と出金用の口座の2つだけにしたり、入出金をひとつの口座にすることで、口座の管理も楽になりますし、資金の流れや残高も把握しやすくなります。
経理担当のよくある悩み
営業担当者との相互理解が得られない!
締切日を守らない営業担当者
経理では厳守するのが当たり前の認識である締切日。会社の利益を得ることが目前の仕事となっている営業担当者は、目標を達成することだけに頭がいっぱいになり、社内ルールである締切日には目が行き届かず、つい後回しにしがちです。
注意しても、一向に改善してくれない営業担当者に苛立つ経理担当者も少なくありません。
「ECRSの原則」に意識が向かず非協力的
業務合理化は経理だけに限ったものではなく、社内部署全体が連携して会社の利益向上のため邁進していく必要があります。「ECRSの原則」に非協力的な営業社員が多数存在していると、いくら経理が頑張ったとしても利益向上は望めません。
その結果、予算オーバーや赤字決算につながるので、精度を高めることのできない経理担当の責任が重く偏ってしまいます。
日付が古い請求書や精算書の後出し
目前の仕事をこなすことだけに意識が集中し、視野が狭くなっている営業担当者は後回しにしていた請求書や精算書を、後からまとめて出してくるケースがあります。日々残業を与儀なくしている経理担当者はたまったものではありません。
無駄は省く!消去法でもっと簡素化させることを第一に
相手に求めてばかりの仕事の仕方では、相互理解が得られないまま解決することは難しいでしょう。
目前の仕事をこなすことに必死になり、他部署のことまで意識がいかないのであれば、次の3つのポイントに注意を向け、無駄を省きお互いの仕事をもっと簡素化することに意識を向けてみましょう。
1.相互の仕事を理解し目的や流れを把握する
なぜこの仕事が必要なのか、どのような目的でおこなわれるのか、まずは互いの仕事内容と目的や流れを掴むことから始めます。
2.必要必須な仕事を洗い出し把握する
この仕事だけは絶対外せないというような内容をすべて洗い出し、その仕事の重要性を理解します。
無駄な仕事の一掃!簡素化することに努める
1や2の工程をおこなうことで、無駄な仕事が見えて、相手のことを考えた仕事のやり方にシフトチェンジすることが可能となります。
日々このような改善を少しずつおこなっていくことで、これまで感じていたストレスを和らげることが期待できるでしょう。
業務フロー見直し
経理業務の効率化を図るためには、業務フローを見直すことから始めましょう。
経理の仕事は大きく分けて、日次、月次、年次の業務があります。
日次の経理業務
- 現金の管理
- 経費の精算
- 預金の管理
- 帳簿、伝票の記入
月次の経理業務
- 請求、支払業務
- 1カ月分の売上や支払の計上
- 支払日の預金残高確認
- 振込や手形、小切手の振出
- 振替伝票の起票
- 給与計算
年次の経理業務
- 決算書作成
- 税金の計算と支払
- 年末調整
- 保険料の計算と申告
これらの経理業務のうち、約80%はルーティンだといわれています。これらの作業をすべて手作業で行うのではなく、ツールやシステムを取り入れて自動化することが、経理業務効率化のポイントです。
業務改善ではなく改革に踏み切る
業務改善は微調整に留まる
これまで解説した内容は業務改善についてです。実は業務改善のパフォーマンスには限界があり、すべてを洗いざらい改善していくことは不可能です。
ただでさえ残業しなければならないほど時間が足りていない現状であるなか、これだけの改善内容を人の手でおこなうとなれば膨大な時間と動力が必要となります。結果、改善できるのは、ほんの10~20%程度が妥当なところでしょう。
このくらいの微調整で上手くいく企業は問題ありませんが、抜本的な改革に踏み切らなければ解決にならない企業も多数あることでしょう。
抜本的な改革の内容とメリット・デメリット
抜本的な改革とは、これまでおこなわれてきたすべての業務を一から再構築することです。システムを導入し、人手不足対策としてのアウトソース化、AIを搭載したロボットなどを活用し業務の効率化を狙います。
メリットは、システムの導入やロボットなどは、人がやるよりも正確でスピーディなので、業務のパフォーマンスをアップさせることが可能となります。
近年、増加傾向にあるアウトソースは、人手不足である経理の人材を外部のプロに委託することで、人件費削減のほか引き継ぎにかかる時間短縮などが期待できます。
デメリットは、すべてをシステム化することができない点です。パターン化できない部分や、自動仕訳の連携にミスが生じた場合など、人の手によるチェックが必要となってくるシーンが出てくることがあります。
社内業務の実情をよく把握し改革をスタートさせる
改革をスタートさせる前に、今の経理の業務内容に足らないもの、必要ないものをしっかり見極めることから始めます。このバランスが偏ってしまうと、システムを導入しても無に帰すことになってしまうからです。
賢い業務フローの見直しをして、確実に働き方改革のできる抜本的改革をシステム化させましょう。
システム化事例
空いた時間に入金以外の業務ができるようになった
業種:基盤システム、Webシステム、クラウドサービスなどの業務管理サービスの開発・提供・サポート
従業員数:約600名
完全手作業で消込作業を行っていましたが、会社の成長に伴い、入金件数が増え、限界を感じ始めていました。
月末日にすべての入金処理をしなければならないため、2,000件ほどの入金を月末は9~18時までかけて3~4名で作業をしていました。
システムを導入したことで、7割ほどの自動消込ができるようになりました。特殊な入金もあり、金額が一致しないこともありますが、得意先の特定は、完全に自動化できています。
業務量も工数も半分以下になり、空いた時間で確認業務ができたり、入金以外の業務もできるようになりました。
入金業務の8割を自動化し作業負荷を50%にまで低減
業種:インターネットによるグリーティングカード、慶弔関連ギフト等通信販売事業など
従業員数:44名
月間1万件の入金情報に対し、銀行が提供する仮想口座サービスを利用して合理化を進めていましたが、エクセルによる手作業で消込作業を行っていたため、煩雑になっていました。
システムを導入することで、入金業務の8割を自動化し、入金が集中する月末の処理も1日以内で作業を完了することができ、作業負荷を50パーセントにまで低減することができるようになりました。
システムの自動照合機能によって、仮想口座サービスの追加投資の必要がなくなり、コストの低減を図ることもできました。
11名で行っていた入金処理が2名でできるようになった
業種:食品の関連資材の製造販売、乳製品の製造販売、フルーツプレパレーションの製造販売
従業員数:約700名
全国8事業所11部門の営業部で請求書業務や入金処理を行っていたため、取引条件や滞留債権情報の共有化ができておらず、統括して管理されていませんでした。また、未回収一覧などの管理帳票作成にも時間がかかっていました。
業務を本社の財務部経理課に集約させたことで、これまで11名で行っていた入金処理が2名で処理することができるようになり、業務の合理化に成功しました。毎日、データで消込処理を行うため、入金の確認漏れや入力ミスがなくなり、業務の正確性の向上にもつながっています。
システムの入金データを月次の資金繰りに利用することで、精度の高い資金繰りもできるようになりました。
債権管理システム導入により
作業効率が上がった事例をもっと見る
債権管理ソリューション「Victory-ONE」
おすすめの債権管理システムは、株式会社アール・アンド・エー・シーの手がける「Victory-ONE」です。オンプレミス型(現地導入型)とクラウド型の双方が用意されており、大手上場企業を含む200社以上の導入実績があります。
Victory-ONEは債権管理全般に対応しているシステムで、開発にあたりとくに注力したのが、請求情報と入金情報を自動照合できる機能。多くの企業が、入金消込の自動化とその精度の高さを理由に導入しています。
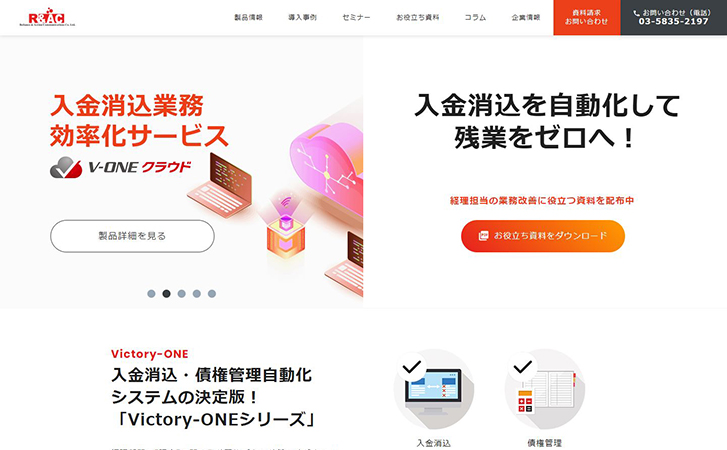
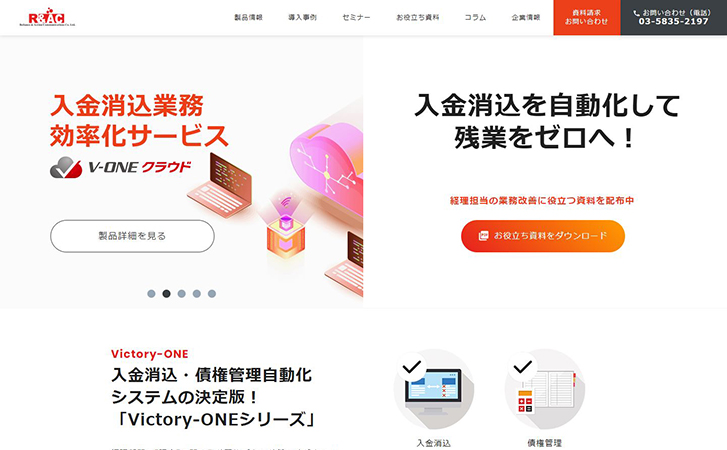
(https://www.r-ac.co.jp/)
既存の会計システムとの連携も可能
「マシンラーニング」を活用した独自の照合ロジックを実装することで、使用すれば使用するほど自動化率・生産性が向上していくシステムを実現。弥生会計、OBIC、TKC、ミロク情報サービスといった、会計システムとの連携も可能です。またSAPやOracleなどのERPとも連携可能となっており、将来的にはSalesforceに対応する計画も視野に入れているとのこと。
クラウドサービス型であれば初期投資も少なく、アカウント数に応じた月額課金方式で利用することができます。申し込み後すぐに利用できるという点も大きな魅力。情報システム部門を持たない企業でも、専任SEによるコンサルティングやサポートを受けることもできます。